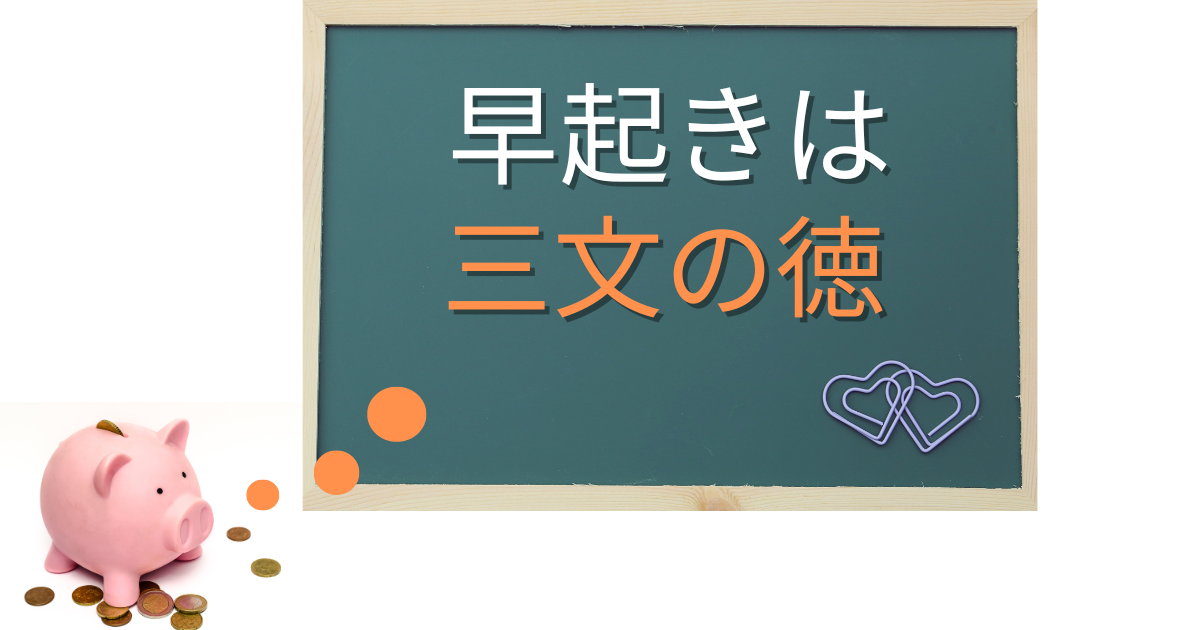子どもの頃、夏休みや冬休みになると「早起きは三文の徳だよ」と親から言われていました。
大人になった今考えると、三文ってどれくらい得なんだろう、と頭でそろばんをはじいてしまう人もいるのではないでしょうか。

これを書いている人がまさにそろばんをはじいてるよ
「早起きは三文の徳」の由来は何なのでしょうか?
三文っていくらなんでしょうか?
「徳」なの?「得」なの?
気になる疑問を調べてみました!
「早起きは三文の徳」どんな意味?
「早起きは三文の徳」を辞書で調べてみました。
早起(はやお)きは三文(さんもん)の徳(とく)
《「徳」は「得」とも書く》早起きをすると健康にもよく、また、そのほか何かとよいことがあるものであるということ。朝起きは三文の徳。
引用元:weblio辞書
上記の意味を読むと、早起きは健康にいいうえに何かいいことが起こるよ、といった意味に捉えられます。
実際に少し早起きをしてみると、外の空気が美味しかったり、普段はやらないことをやってみようと思ったり、プラスアルファの体験をすることがあります。
「三文」の言葉に引っ張られて金銭的な得をイメージする方もいると思いますが、少し意味合いが異なるようですね。
ちなみに、「三文」は江戸時代のお金である一文銭3枚分で、今で言うと100円くらいの価値です。

「三文」自体が価値が低い、価値がない、といった意味があるよ
「早起きは三文の徳」由来は?
「早起きは三文の徳」の由来は諸説ありますが、共通している部分もあります。
それは、中国の宋時代に活躍した詩人、楼鑰(ろうやく)が書いた詩の一節、「早起三朝當一工」がもとになっていることです。
これには、「早起きを3日続ければ、1人分の働きになる」という意味があります。
おおもとの意味は上記のとおりですが、これを受けて日本では「奈良説」と「高知説」が生まれました。
奈良説
江戸時代、第5代将軍徳川綱吉が制定した「生類憐みの令」により、動物が保護されていました。
奈良県では鹿も保護対象だったため、危害を加えた者は三文の罰金が科されました。
そのため、
- 庶民は朝早起きして家の前に鹿の死骸がないかを確認し、
- 万が一あった場合は隣の家の前に移動させ、
- それが繰り返されて一番遅く起きて家の前に死骸のあった家庭が罰金を支払った
という逸話が残っています。
このことから、朝早起きすれば三文の罰金を払わなくて得をする、という説が生まれました。

だから「三文の得」なんだね
高知説
一方で高知説はこうです。
当時の土佐藩が治水対策のために早く堤防を築こうとしていました。
少しでも早く土を固めるため「堤防の土を朝早く踏み固めた者には三文を与える」というお触れを出しました。
このお触れが由来となったのが高知説です。

すごくシンプルな由来だね
「徳」と「得」、どちらが正しい?
これまでの由来を考えると、「徳」も「得」もどちらも正しいことがわかります。
おおもとの中国由来部分では「徳」、日本に入ってきた後の由来では「得」がしっくりきますね。
「早起きは三文の徳」の例文
まとめ
ここまで「早起きは三文の徳」の意味と由来をみてきました。
奈良説の話はツッコミどころがありますが、当時の金銭事情を考えると納得できます。
皆さんも「早起きは三文の徳」を実践して、健康&プラスアルファのいいことを手にしましょう!

周りの人にも教えてあげよう!